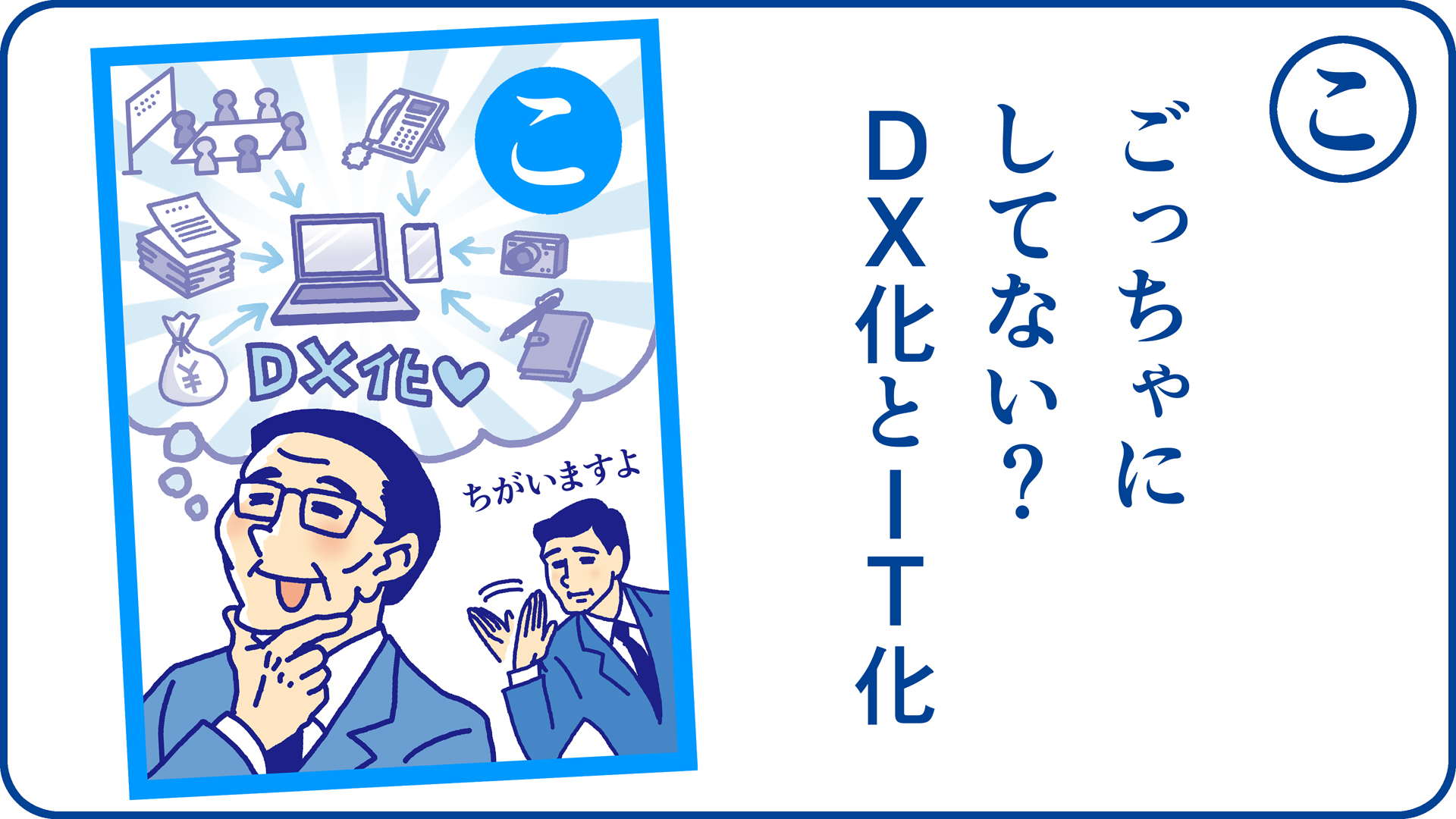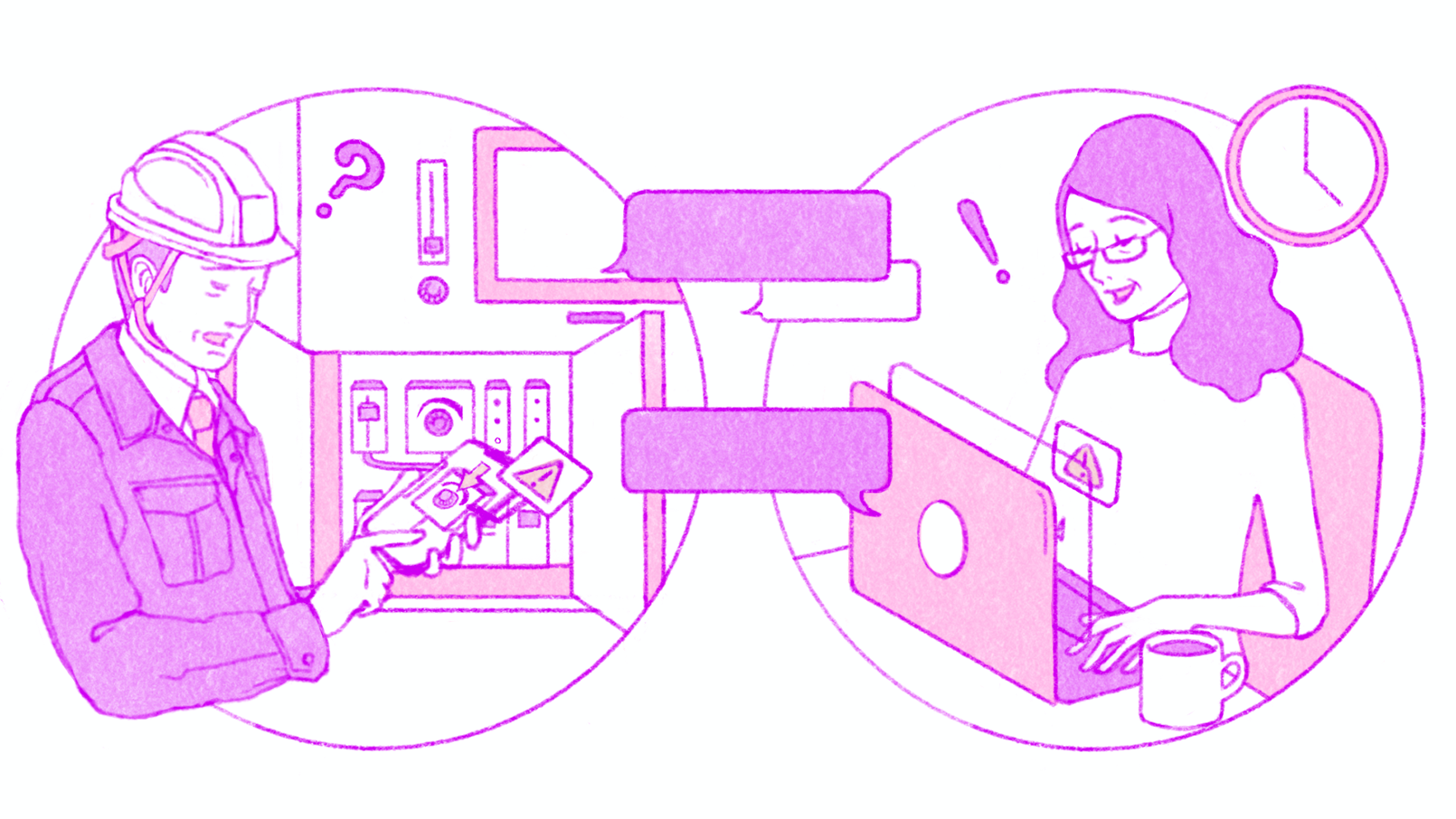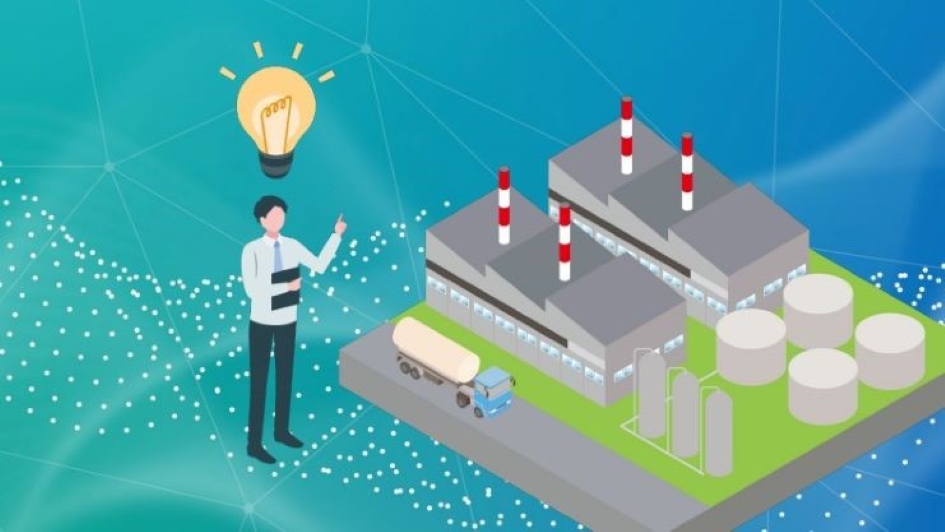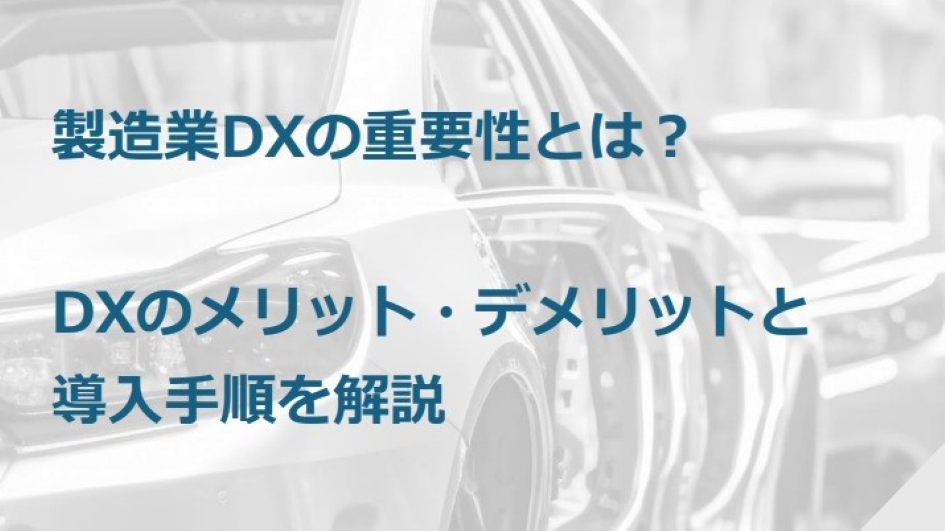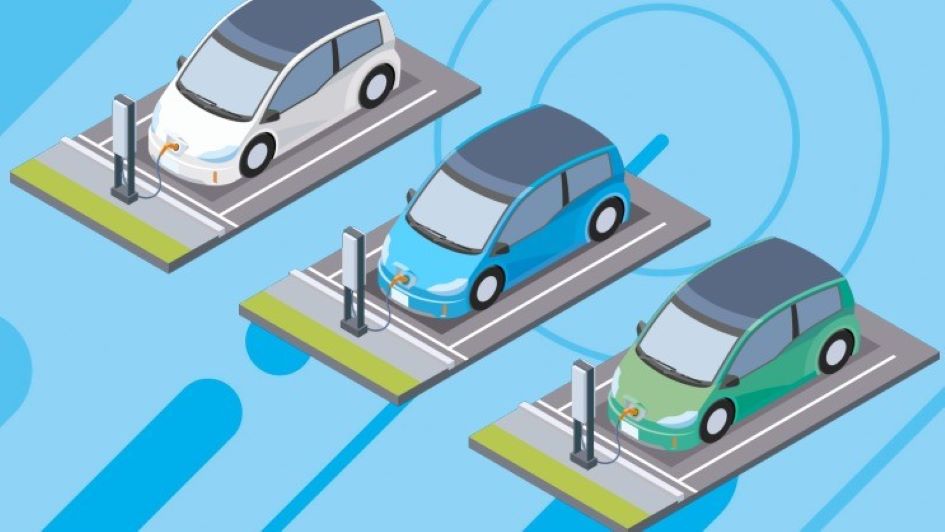「仮想現実」とも呼ばれるVR(Virtual Reality)は、仮想空間内でリアルな体験を提供する技術です。VRゴーグルをはじめとした専用のデバイスを使い、ユーザーを仮想現実に没入させます。この技術を盛り込むことで、現実には不可能な体験が可能です。
本記事では、VRが実際にどのように活用されているのかや、メリット・デメリットについて事例をもとに紹介します。事例を参考にしながらVRを活用し、ビジネスチャンスを広げたいと考えている方は、最後まで記事をご覧ください。
VRとは仮想現実を体験する技術のこと
VR(Virtual Reality)は「仮想現実」とも呼ばれ、コンピューターを用いて仮想空間を再現し、ユーザーをその中に没入させる技術を指します。専用のゴーグルを使用し、体の動きや視覚・聴覚をリアルタイムで反映させることで、ユーザーはまるで別世界にいるかのような体験が可能です。
近年ではビジネス・教育・医療などさまざまな分野でVRが活用され、リアルな体験や訓練・コミュニケーションの手段として注目されています。
VRについては下記の記事で詳しく紹介しているため、あわせてご参照ください。
VRとは|仕組みやAR・MRとの違い、体験方法まで徹底解説!
VR活用の身近な例を業界別に紹介
VR活用の身近な例を業界別に紹介します。
・VR活用の身近な例1.ビジネス
・VR活用の身近な例2.教育
・VR活用の身近な例3.医療
それぞれ、詳しくみていきましょう。
VR活用の身近な例1.ビジネス
ビジネスシーンでのVR活用は多岐にわたります。例として次のような活用方法があります。
・商品の体験販売やプロモーション:顧客が商品を仮想空間内で試着・体験し、購買意欲が高まる
・研修やトレーニング:リアルなシミュレーションを通じて、安全かつ効果的にスキルや手順を習得できる
・遠隔コミュニケーション:地理的な距離を超えて、リアルタイムの会議やコラボレーションが可能となる
・製品のデザインや開発の簡略化:VRを活用してデザインや開発の工程を短縮できる
仮想空間でリアルな体験ができるVRの特徴を活かし、企業は競争力を高め、お客様や取引先との関係強化が可能です。
VR活用の身近な例2.教育
教育現場では、VRが革新的な学習環境を提供しています。
・体験型学習:VRを活用した授業を生徒が体験することで学びが深まる
・遠隔授業:VR空間を活用して、教室に行かなくても都合の良い時間に学習できる
・学びの質の向上:VR空間でゲームのように楽しみながら学べるようになる
VR空間では、教育をゲームのような感覚で楽しむことが可能です。これにより、教育の効果を最大限に高め、生徒たちがより豊かな学びを得られるようになります。
VR活用の身近な例3.医療
医療現場でも、VRは幅広く利用されています。
・手術シミュレーション:手術のプランニングや技術の習得にVRを活用
・患者のリハビリテーション:VR空間内で運動療法や認知療法を行うことにより効果が高まる
・患者自身の健康状態理解:イメージが難しい患者自身の健康状態を、VRにより視覚的に理解できる
・遠隔治療への活用:地域格差や移動が難しく、治療を受けることが困難な患者への治療の実現が期待されている
VRの「体験する」技術は、病状の説明やリハビリテーション時など、さまざまな場面で役立ちます。VRを効率的に活用することで、より質の高い医療サービスの提供が可能です。
VR技術の活用事例5選
VR技術の活用事例を5つ紹介します。
・事例1.アバターを通じてお客様とコミュニケーション:株式会社ローソン
・事例2.大学をバーチャル化:バーチャル東大(東京大学)
・事例3.研修にVRを導入:日本KFCホールディングス株式会社
・事例4.VRで工場見学:アサヒビール株式会社
・事例5.店舗をバーチャルショールーム化:株式会社ニトリホールディングス
それぞれの事例について詳しくみていきましょう。
事例1.アバターを通じてお客様とコミュニケーション:株式会社ローソン
20を超えるサステナブルな施策を集約した「グリーンローソン」がオープンした2022年の11月に導入されたのが「アバター接客」です。
「アバター接客」とは、離れた場所からオンラインでつながったスタッフが、カメラに映る来店客に対しアバターを通して接客するサービスです。アバター接客のスタッフ募集には、10代から60代まで約400人の応募がありました。なかには「『介護がある』などの理由から店舗勤務はできないが、オンラインで接客をしたい」という声もあったようです。
グリーンローソンの「アバター接客」にとどまらず、AR・VR・ロボットなど複数の技術を組み合わせれば、品出しや商品チェック・簡単な調理など、より能動的にさまざまな仕事ができるようになるでしょう。これらの技術があれば、ひとりが同時に複数店舗で勤務することも可能となり、コスト削減や人材不足の解消が期待できます。
参考:「グリーンローソン」オープン。運転免許+セルフレジで酒・アバター接客|Impress Watch
事例2.大学をバーチャル化:バーチャル東大(東京大学)
東京大学の「バーチャル東大」は、リアルな東大のキャンパスを再現したオンラインプロジェクトです。このバーチャルキャンパスでは、実際の建物や教室・施設が再現されています。ユーザーは仮想空間内で授業やイベントに参加したり、キャンパスツアーを楽しんだりできます。
オンラインプロジェクトの目的は、遠隔地に住む学生や身体的な制約のある人々に、東大の教育やキャンパスライフを体験する機会を提供することです。ユーザー同士でのコミュニケーションやグループ活動も仮想空間内で行えます。
バーチャル東大は、教育のアクセシビリティを向上させるだけではありません。遠隔地にいる学生が実際のキャンパスに足を運ぶことなく、東大の雰囲気や環境に触れる機会を提供しています。プロジェクトは現在も進行しており、学園祭やオープンキャンパスなどの活用に向けてシステムを開発中です。
参考:バーチャル東大|東京大学
事例3.研修にVRを導入:日本KFCホールディングス株式会社
日本KFCホールディングス株式会社は、2017年からVRを活用した研修を導入しています。この研修は、ケンタッキーフライドチキン(通称KFC)の新人従業員やエリアマネージャーが、フライドチキンの作り方を学ぶことを目的としています。
VR研修の導入により、従業員は研修にかかる時間を大幅に短縮し、楽しみながら効果的に学ぶことが可能です。また、場所や回数に制限がなくなり、どこでも研修を実施できる利便性もあります。結果として、研修のコスト削減や従業員のスキル向上につながりました。
KFCのVR研修は、業務効率化や教育効果の向上を実現しています。
参考:VRをケンタッキーが研修で活用!kfcで行っている研修を紹介!|Spacely
事例4.VRで工場見学:アサヒビール株式会社
アサヒビール株式会社は、ビールの価値再発見と特別な体験を提供するため、2020年5月21日から特設Webサイトで「アサヒスーパードライVR工場見学」を無料公開しています。
この工場見学では、参加者が実際のビール工場の様子を仮想現実でリアルに体感可能です。工場内の機械や作業手順など、ビール製造の全工程をすぐ側にいるかのように見学できます。参加者は、VRゴーグルを装着し、工場内を歩き回りながらビールの醸造過程を観察できます。
VR工場見学は、VR専用ゴーグルやスマートフォン・パソコンなどを用いて、YouTubeアプリで視聴可能です。
事例5.店舗をバーチャルショールーム化:株式会社ニトリホールディングス
株式会社ニトリは、ニトリ・デコホーム・ニトリビジネスの3つのセクションをバーチャルショールーム化しました。このショールームにおいて、顧客は360°の視野でショールーム内を移動し、好みのコーディネートを見つけられます。インテリア商品にピンがついており、詳細を一覧で確認しながら直接購入可能です。
また、ニトリ中目黒通り店をバーチャルショールーム化し、店舗にいるような感覚で買い物を楽しめることも特徴の一つです。これにより、全国の顧客がオフィス家具や関連商品を気軽に確かめられます。
VRがもたらすメリット4選
VRがもたらすメリットは主に4つあります。
・メリット1.リアルに近い体験が可能になる
・メリット2.表現の幅が広がる
・メリット3.時間や場所にとらわれずに体験ができる
・メリット4.時間やコストの削減が期待できる
それぞれについて、詳しくみていきましょう。
メリット1.リアルに近い体験が可能になる
VRではリアルにより近い体験が可能です。たとえば、部屋にいながら世界中を旅しているような体験や、コンサートホールで音楽を聴いている体験ができます。
また、コントローラーのようなツールを使用し、実際に触れたような体験も実現可能です。視覚だけではなく触感も体験できるため、深い没入感を得られます。
メリット2.表現の幅が広がる
VRを活用することで、表現の幅が広がります。仮想空間の特性から、リアルな場所だけではなく、実在しない場所や過去の建造物なども再現可能です。これにより、さまざまな分野で新しいアイデアやコンセプトを実現し、創造性を発揮できます。
製品やサービスの開発段階での利用も可能です。ユーザーが製品やサービスを仮想空間で試すことで、ユーザーに寄り添った開発が促進されます。なぜなら、VRの表現力を活かすことで、より革新的なアプローチや体験を提供できるようになるからです。
VRを活用し、ユーザーが求める商品やサービスを提供できれば、顧客満足度アップにもつながるでしょう。
メリット3.時間や場所にとらわれずに体験できる
時間や場所にとらわれずにリアルな体験ができることもVRのメリットの一つです。たとえば、遠隔地に住む人々が仮想空間でリアル会議を行ったり、生徒が教室にいながら世界各地の名所を訪れたりできます。
また、VRを活用すれば、リスクを最小限に抑えながら訓練や学習も可能です。
メリット4.時間やコストの削減が期待できる
遠隔地での会議やトレーニングなどを仮想空間で実施すれば、移動時間や交通費がかかりません。さらに、リアルな環境での試行錯誤や実験を仮想空間内での安全な環境で行えることも、時間やコストの削減につながるでしょう。
VRを活用し、時間やコストを削減できれば、企業は効率的に活動できるようになり、収益アップも期待できます。
VRがもたらすデメリット4選
VRには、考えられるデメリットが4つあります。
・デメリット1.VRに酔うおそれがある
・デメリット2.専用のデバイスが必要になる
・デメリット3.撮影時の環境に細心の注意が必要になる
・デメリット4.ネットワーク環境の影響を受けやすい
VRの活用を検討する際は、デメリットも十分に考慮することが重要です。詳しくみていきましょう。
デメリット1.VRに酔うおそれがある
VRを体験すると、乗り物酔いのような感覚に陥るおそれがあります。VR酔いは、視覚が動いているにもかかわらず体が動いていないため、感覚のずれが生じてめまいや吐き気などを引き起こす現象です。
VR酔いの対策方法として以下が挙げられます。
・長時間使用しない
・アクションやゲームのような酔いやすいコンテンツは避ける
・使用するゴーグルを変更する(二眼ゴーグルのほうが酔いやすいため)
VRを快適に活用するためには、VR酔いへの十分な対策が必要です。
デメリット2.専用のデバイスが必要になる
VRを体験するには、ゴーグルをはじめとした専用のデバイスが必要です。
VRゴーグルには「PC接続型」「スマホ取り付け型」「スタンドアロン型」があり、それぞれ性能が異なります。また、VR映像を撮影するときにも、スタビライザー付きのプロ仕様のカメラを用意しなければなりません。
デメリット3.撮影時の環境に細心の注意が必要になる
実際の風景や建物を利用したVRの場合、撮影時に余計なものが入り込まないように細心の注意が必要です。
VRは、人や撮影機材・照明の不自然な光などの余計なものが入り込むと没入感が薄れてしまいます。さらに、VRは360℃すべてが撮影対象になるため照明が使えません。
VRの撮影時は、企画段階から光の具合や人の配置などの綿密な打ち合わせが重要です。
デメリット4.ネットワーク環境の影響を受けやすい
VRを楽しむためには、大容量かつ安定したネットワーク環境が必要です。
VRはデータ通信量が大きいため、ネットワーク環境が安定していないと遅延しやすい特徴があります。不安定なネットワークにより映像がカクカクしていると、没入感が薄れてしまうため注意しなければなりません。
とくに、モバイルやWi-Fi環境では遅延が起こりやすくなります。VRを楽しむためには有線の光回線がおすすめです。
VRとリモートサポートサービスで広がる可能性
VRの活用が広がれば、リモートでの仕事やコミュニケーションがさらに増えると予想されます。そこでおすすめしたいのが、ユーザーの支援を遠隔地から行えるリモートサポートサービス『Splashtop SOS』『Splashtop AR』の導入です。
Splashtop SOSは、担当者が現地に赴かなくてもサポートできるツールです。電話番号などの個人的な連絡先を共有しなくてもサポートが可能なVoice Call機能や、多くの企業が採用しているMicrosoft Teamsとの連携など、リモートサポートに必要な機能を備えています。
Splashtop ARは、スマホやタブレットなどの映像を、遠隔で別のデバイスに映し出せるツールです。トラブルシューティングやセットアップなどを視覚的に把握しながら、ピンポイントでリモートサポートできます。
今後は、SplashtopとVRの連携も視野に入れています。もし実現すれば、カフェでのリモートワークの形式も変わるでしょう。MacBookを持ち込んでの作業ではなく、PCを持たずにVRゴーグルを装着しておしゃれに働く人が増えるかもしれません。キーボードもバーチャルで操作できるため、空中で指を動かしながら操作するという未来も考えられます。現在は少し異様な光景に思えますが、それが当たり前になると、社会は変わります。専用のカフェができ、PCを持ち歩くことが時代遅れの世の中が来るかもしれません。
SplashtopとVRの連携については下記のインタビュー記事で詳しく紹介しているため、あわせてご参照ください。
スプラッシュトップ株式会社の中の人が試して考えた!VRゴーグルとSplashtop連携で広がる新しい働き方
このように『Splashtop SOS』『Splashtop AR』は、大きな可能性を秘めています。気になる方は、ぜひ下記のリンクから詳細を確認してみてください。
Splashtop SOSを詳しく知る Splashtop ARを詳しく知る
VRを効率良く活用して視野を広げよう
近年、VRはさまざまな分野で活用されるようになりました。VRを効率良く活用できると視野が広がり、企業が大きく成長する可能性があります。VRのメリットとデメリットをよく理解し、自社のビジネスに活用できるかを検討してみてください。
Splashtopが提供するワンタイムリモートサポートツール『Splashtop SOS』『Splashtop AR』では、技術者が現地に赴かなくても遠隔で問題解決や技術指導を行えます。「場所」という制約がなくなるため、技術者にとってもユーザーにとっても、利便性の高いツールです。
SplashtopのツールはVRとの連携も視野に入れています。リモートサポートツールがVRと連携することにより、働き方も大きく変わるかもしれません。
リモートサポートに興味のある方や、現在の保守・点検作業を改善したい方は、Splashtopのリモートサポートツールの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
気になる方は、ぜひ下記よりお問い合わせください。